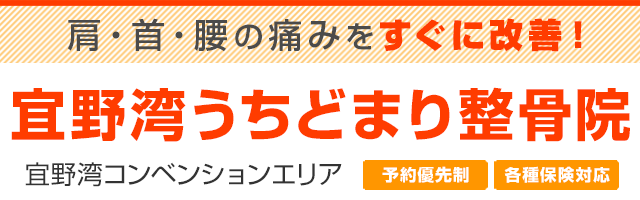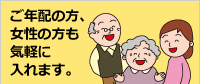眼精疲労


こんなお悩みはありませんか?

充血
目がかすむ
目が重い
目の奥の痛み
ドライアイ
瞼が開きにくい
1日何時間も同じ姿勢でモニター画面を見続けることで目の疲れが蓄積し、全身の不調を伴うケースが多くなっています。現代病の代表例です。
単なる疲れ目であれば1~2日ぐっすり眠ると回復することが多いですが、休んでも回復せず慢性的に続く疲れを「眼精疲労」といい、ただの疲れ目とは区別されます。
眼精疲労についてで知っておくべきこと

眼精疲労は疲れ目がさらに進行した状態で、症状も重くなります。目がかすむ、目が重い、充血する、目の奥の痛み、ドライアイ、まぶたが開きにくくなるなどの症状に加え、頭痛や肩こり、吐き気、不眠、食欲や集中力の低下、全身の倦怠感や軽いうつ状態など、全身症状を伴う場合もあります。症状の進行度によって重症化しやすくなるため、注意が必要です。
40代以降は水晶体の厚さを変えるピント調節機能が衰えます。加齢によって筋肉が硬くなり、身体の血行が悪くなるように、水晶体の周りの毛様体筋も硬化して動きが悪くなります。
症状の現れ方は?

目に充血や痛みなどが起こり、視界がかすみ・ぼやける、まぶしさを感じるなどの症状が現れます。これが悪化すると目の症状だけではなく、きつい肩や首の凝りが生じ、ときにはめまいや吐き気など、全身に不調を感じることもあります。
このような症状が十分な休息をとっても回復しない場合、それは眼精疲労であり、通常の疲れ目とは区別して考えるべきです。
近年ではパソコンなどのディスプレイ作業が増え、近い距離にピントを合わせるために目の筋肉を使い続けてしまうことが原因となる眼精疲労が増加しています。
ただの疲れ目と軽視していると、身体だけでなく心にも影響を及ぼすことがあります。
その他の原因は?

眼精疲労とは、目だけでなく全身にも疲労を感じてしまう状態を指します。眼精疲労は、単なる疲れ目とは区別して考えることが重要です。
主にテレビやパソコン、スマートフォンなどの画面を長時間見続けること、メガネやコンタクトレンズの不具合、目の病気などが原因となりますが、全身の疾患や精神的なストレス、疲労などが原因である場合もあります。現在では、ブルーライトカットのスマートフォンのフィルムカバー、メガネ、サングラスのレンズなど、目へのストレスを軽減してくれるアイテムも増えてきています。
目の疲れやその他の症状が長く続く場合、原因を特定し、根本から施術を行うことが軽減のカギとなります。
眼精疲労を放置するとどうなる?

眼精疲労を放置すると、さまざまな症状が現れることがあります。例えば、目が疲れると目の周りの筋肉が緊張し、それが全身の筋肉に伝わり、肩こりや首こりにつながることがあります。また、眼精疲労がひどくなると、自律神経のバランスが乱れ、精神的なストレスや頭痛、胃腸の不調、吐き気など、さまざまな症状が現れることもあります。
近年では、スマートフォンやタブレット、パソコンの普及により、以前よりも目を使う機会が増え、それが原因で眼精疲労が進行することが増えています。そのため、目を定期的に休めたり、寝る前にスマートフォンを使わないようにするなど、目を守ることが何よりも大切です。
当院の施術方法について

1. ドライヘッド
人の頭皮には、眼精疲労に効果が期待できるツボが多く存在しています。当院のドライヘッド矯正では、頭皮・額・頸などのツボを刺激することにより、眼精疲労の軽減はもちろん、眼精疲労からくる頭痛やこり、自律神経の乱れなどの症状の軽減が期待できます。
改善していく上でのポイント

眼精疲労を軽減するためには、まず、疲労感を残さないことが重要です。疲れを残さないためには、目の使いすぎや老廃物を取り除くことが必要です。
例えば、画面の明るさは周囲に合わせ、目から50~70センチメートル離すのが理想的です。また、まばたきの回数を増やして目の乾燥を防ぎましょう。ブルーライトカットのフィルターや眼鏡も効果が期待できます。
部屋の湿度を保ち、目薬を使うことで乾燥を防ぐことも大切です。さらに、眉間の間のツボを刺激することで老廃物を血流に流すことができます。
眼精疲労は目からの辛さだけでなく、首や肩こりから症状につながることも多いため、デスクワークを行う方は姿勢にも注意が必要です。
監修

宜野湾うちどまり整骨院 院長
出身地:群馬県前橋市
趣味・特技:ラーメン巡り